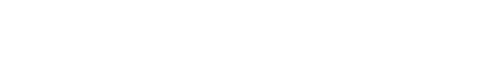「家を出ると愛犬がずっと吠えている」「姿が見えなくなると不安そうに鳴く」──そんな行動が見られたら、それは分離不安症(Separation Anxiety)のサインかもしれません。
本記事では、犬の分離不安症の原因・症状・改善方法をわかりやすく解説します。
■ 分離不安症とは
分離不安症とは、飼い主と離れることに強い不安やストレスを感じる状態を指します。
特に留守番の際に落ち着かず、吠え続けたり物を壊したりする行動が見られる場合は要注意です。
おおよそ30分以上ひとりで留守番できずに鳴き続ける犬は、分離不安症の可能性が高いとされています。
■ 分離不安症の主な症状
以下のような行動が頻繁に見られる場合は、分離不安症を疑いましょう。
- 飼い主の後を常に追いかける
- 外出時に落ち着かず、吠える・うなるなどの行動を見せる
- 留守中に家具を噛む、物を壊すなどの破壊行動
- 排泄の失敗(普段できていたトイレができない)
- 飼い主の帰宅時に過剰に興奮し、ジャンプやお漏らしをする
重度になると以下のような身体的な症状も現れます。
- 自分の体を過剰に舐める
- 下痢や嘔吐が続く
- 被毛の状態が悪化する
- 元気がなく、うつ状態になる
■ 分離不安症の原因
分離不安症の原因は、犬の性格や飼い主との関係性、生活環境の変化など多岐にわたります。
- 幼犬期にひとりで過ごす経験が少ない
- 飼い主の過度なスキンシップや依存関係
- 引越し・転職・家族構成の変化など、生活リズムの急な変化
- 外出や帰宅のたびに過剰な反応をしている
こうした環境の積み重ねによって、犬は「飼い主がいない=不安」という学習をしてしまいます。
■ 飼い主ができる改善方法
分離不安症は、愛犬の接し方を見直すことで徐々に改善できます。以下の方法を試してみましょう。
① 外出を悟らせない工夫を
鍵を取る・コートを着るなどの“外出のサイン”を日常的に行い、外出=特別な出来事ではないと犬に学習させます。
また、外出の直前は愛犬に構わず、静かに出かけることが大切です。
② 留守番の練習を段階的に
最初は5分ほどの短時間からスタートし、少しずつ留守番の時間を延ばしていきます。
愛犬が落ち着いて過ごせたら、静かに褒めてあげましょう。
③ 帰宅時はあえて“無関心”に
帰宅直後に興奮している場合は、落ち着くまで声をかけない・触らないことがポイントです。
過剰な愛情表現を控えることで、犬が精神的に自立しやすくなります。
④ 安心できる居場所を作る
犬がひとりでも落ち着ける空間を用意しましょう。
クレートやベッドを静かな場所に設置することで、「ここにいれば安心」と感じさせることができます。
⑤ 専門家に相談する
症状が重い場合は、獣医師やドッグトレーナーに相談を。
薬による不安緩和と行動療法を併用することで改善が早まるケースもあります。
■ 分離不安症は改善できる
分離不安症は先天的なものではなく、環境と接し方で変えられる行動パターンです。
正しい知識と愛情をもって向き合えば、時間をかけて改善していくことができます。
(監修:NPO法人アニマルワン)
Nature Cottage Akabekoのご紹介

福島県北塩原村・裏磐梯にあるNature Cottage Akabekoは、ペットと一緒に宿泊できる自然豊かなコテージ宿です。
広大な人工芝ドッグランを完備し、超大型犬まで宿泊可能。
四季折々の美しい景色と穏やかな環境で、愛犬とリラックスしたひとときをお過ごしいただけます。
旅行中でも愛犬のストレスケアを大切にしたい方におすすめです。
▶ 詳しくはこちら:Nature Cottage Akabeko公式サイト